二世帯住宅を建てるにはどのくらいの間取りと広さが理想的?
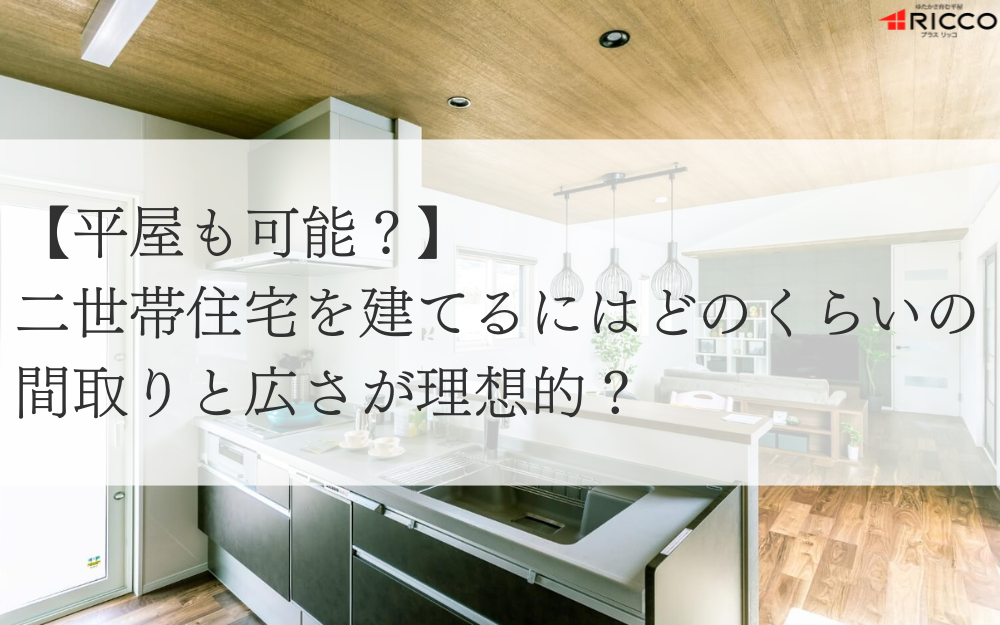
この記事では、二世帯住宅に必要な広さの目安から、平屋と2階建ての違い、間取りパターン別のメリット・デメリットまで、二世帯住宅を成功させるためのポイントを詳しく解説します。
注文住宅で理想の二世帯住宅を実現したい方は、ぜひ参考にしてください。
1. 二世帯住宅に必要な広さの目安
一般的な二世帯住宅の坪数
ただし、この数値はあくまで目安であり、実際は家族構成や選択する間取りパターン、土地の形状などによって大きく変わります。
重要なのは単純に面積の広さだけでなく、それぞれの世帯が快適に暮らせる空間設計ができているかどうかです。
例えば、完全分離型の場合は一つの建物内に独立した2つの住戸を設けるため、より多くの面積が必要になります。
一方、部分共有型や完全同居型では、共有スペースを上手に活用することで、コンパクトな面積でも快適な住環境を実現できます。
※1 参考:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」
家族構成別の適正面積
二世帯住宅の適正面積は、それぞれの世帯の家族構成によって決まります。子世帯が夫婦のみの場合と、小さなお子様がいる場合では必要な面積が大きく異なるためです。
親世帯2名・子世帯2名(夫婦のみ)の場合
延床面積:45~50坪程度
各世帯にLDK、寝室1室、浴室、トイレが必要な最小構成です。この場合でも、将来お子様が生まれることを想定して、子世帯側に余裕のある間取りを考えておくと良いでしょう。
親世帯2名・子世帯4名(夫婦+子ども2人)の場合
延床面積:55~65坪程度
子世帯側に子ども部屋2室が必要になるため、全体の面積が大きくなります。また、家族が増えることでリビングも広めに確保したいところです。
親世帯3名・子世帯5名の場合
延床面積:65~75坪程度
両世帯ともに人数が多い場合は、相当な面積が必要になります。この場合、平屋での実現は土地の関係で困難な場合が多く、2階建てでの検討が一般的です。
これらの数値は、あくまで目安であり、実際の暮らし方や価値観によって必要な面積は変わります。重要なのは、家族全員が快適に過ごせる空間づくりです。
平屋と2階建ての面積比較
平屋の二世帯住宅の特徴
平屋の場合、建築面積(1階部分の面積)=延床面積となるため、広い土地が必要になります。例えば、50坪の二世帯住宅を平屋で建てる場合、建物だけで50坪の土地面積が必要です。
しかし、平屋には大きなメリットがあります。
すべての生活空間が同じフロアにあることで、親世帯・子世帯間のコミュニケーションが取りやすく、お互いの気配を感じながら適度な距離感を保てます。また、バリアフリー対応が容易で、将来的な介護や生活支援の面でも安心です。
2階建ての二世帯住宅の特徴
2階建ての場合、例えば50坪の延床面積でも、建築面積は25坪程度に抑えることができます。そのため、限られた土地でも効率的に必要な住空間を確保できます。
2階建てのメリットは、1階に親世帯、2階に子世帯といった明確なフロア分けができることです。プライバシーを重視したい場合や、生活リズムの違いを考慮したい場合に適しています。

2. 二世帯住宅の間取りパターン別メリット・デメリット
完全分離型の特徴と必要面積
完全分離型の二世帯住宅は、一つの建物内に独立した2つの住戸を設ける形式です。
それぞれの世帯が完全に独立した暮らしができるため、プライバシーを重視したい家族に人気があります。
完全分離型のメリット
・各世帯が完全に独立した生活ができる・生活音やニオイなどの干渉がない
・将来的に賃貸や売却がしやすい
・住宅ローン控除を各世帯で受けられる可能性がある
完全分離型のデメリット
・建築費用が最も高くなる・広い土地と大きな建物が必要
・光熱費や設備機器の維持費が2軒分かかる
・家族間のコミュニケーションが取りにくい場合がある
完全分離型の場合、延床面積は60坪以上が理想的とされています。平屋で実現する場合は、建築面積も60坪程度必要になるため、100坪以上の土地が望ましいでしょう。
部分共有型の特徴と必要面積
部分共有型は、玄関や浴室、キッチンなどの一部を共有しながら、寝室やリビングは独立させる形式です。完全分離型と完全同居型の中間的な位置づけで、バランスの取れた選択肢として人気があります。
部分共有型のメリット
・共有部分でのコミュニケーションが自然に生まれる
・光熱費や維持管理費の節約ができる
・家事の協力や子育てサポートが受けやすい
部分共有型のデメリット
・共有部分の使い方でトラブルが起きる可能性・生活時間の違いが影響する場合がある
・建物の構造上、将来の独立が困難
部分共有型の場合、延床面積は50~60坪程度で実現可能です。共有する設備や空間によって面積調整ができるため、土地の条件や予算に合わせた柔軟な設計ができます。
完全同居型の特徴と必要面積
完全同居型は、リビングやキッチン、浴室などすべての設備を共有する形式です。
昔ながらの大家族スタイルで、家族との距離の近さを重視したい場合に選ばれます。
完全同居型のメリット
・建築費用が最も抑えられる・家族間のコミュニケーションが密
・子育てや介護の協力が得られやすい
・光熱費や維持管理費が1軒分で済む
完全同居型のデメリット
・プライバシーの確保が困難・世帯間の価値観の違いがストレスになる可能性
・生活音やニオイなどの問題が起きやすい
・将来的な独立や売却が困難
完全同居型の場合、延床面積は45~55坪程度で実現可能です。ただし、家族全員が快適に過ごせるよう、個室の配置やリビングの広さには十分な配慮が必要です。
3. 平屋の二世帯住宅を選ぶメリット
バリアフリー設計で将来も安心
親世帯にとって、年齢を重ねるごとに階段の昇り降りは大きな負担となります。特に膝や腰に不安を感じるようになった場合、2階建ての住宅では日常生活に支障をきたす可能性があります。平屋なら、そうした心配がありません。
プラスリッコの平屋住宅では、段差のないフラットな設計を基本とし、将来的に手すりの設置や車椅子での移動も想定した設計を行っています。
廊下幅も余裕をもって確保し、ドアの開閉も引き戸を多用するなど、バリアフリーに配慮した住まいづくりを心がけています。
家族のコミュニケーションが取りやすい
平屋の二世帯住宅では、すべての生活空間が同じフロアにあることで、親世帯と子世帯の自然なコミュニケーションが生まれます。
完全に独立した暮らしを求める場合は別ですが、適度な距離感を保ちながら家族の絆を大切にしたい場合には、平屋の空間構成が大きなメリットとなります。
例えば、キッチンで料理をしている時に、リビングで過ごす親世帯の様子を見守ることができたり、子どもが遊んでいる様子を祖父母が見守ることができたりと、世代を超えた自然な交流が生まれます。
プラスリッコの「アトリエ博多」モデルハウスでは、中庭を中心とした間取りで、各世帯のプライベート空間を確保しながら、共有できる空間も設けています。
リビングから中庭が見渡せる設計により、屋外での子どもの遊びを室内から見守ることができるなど、安心で快適な二世帯住宅の暮らしを体感していただけます。
構造的に安定で地震に強い
特に二世帯住宅では、建物が大型になることが多いため、構造の安定性は重要な検討ポイントです。平屋なら、大きな建物でも重心が低いため、安心して暮らすことができます。
また、屋根や外壁のメンテナンスも2階建てに比べて容易です。将来的な維持管理の負担軽減という観点からも、平屋には大きなメリットがあります。
4. 二世帯住宅の間取り設計で失敗しないポイント
プライバシーを確保できる動線計画
二世帯住宅で最も大切なのは、お互いのプライバシーを尊重できる動線計画です。同じ建物内に住んでいても、それぞれの世帯が快適に過ごすためには、適切な距離感を保てる間取りが必要です。
玄関の配置について
玄関を共有する場合と分離する場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。共有する場合は建築費用を抑えられますが、来客時や外出時の時間が重なるとストレスになる可能性があります。分離する場合は、それぞれの世帯が独立した生活を送れますが、建築費用は高くなります。
寝室エリアの配置
寝室エリアは各世帯のプライベートゾーンです。生活音が伝わりにくい配置を考えることが重要です。例えば、子世帯の寝室の真上に親世帯の寝室を配置すると、夜間の生活音が気になる場合があります。
共有スペースと個室のバランス
リビングやダイニングなどの共有スペースは、家族が自然に集まれる配置にしつつ、個室への動線はプライバシーを確保できるよう配慮することが大切です。
光熱費を抑える設備の共有範囲
二世帯住宅では、どの設備を共有し、どの設備を分離するかによって、建築費用と維持管理費が大きく変わります。バランス良く判断することで、コストを抑えながら快適な暮らしを実現できます。
給湯設備の共有について
給湯設備を共有する場合、初期費用は抑えられますが、使用量に応じた費用分担の方法を決めておく必要があります。エコキュートなどの高効率給湯器を導入する場合は、容量を大きめにすることで光熱費の削減効果が期待できます。
電気・ガス・水道の契約方法
完全分離型の場合は個別契約が可能ですが、部分共有型の場合は共有部分の使用料を どのように分担するかを事前に決めておくことが重要です
プラスリッコでは、ご家族の生活スタイルに合わせた最適な設備計画をご提案しています。
例えば、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、二世帯分の電力をまかないながら光熱費を大幅に削減することも可能です。
将来の家族構成変化に対応できる柔軟性
家族構成は時間とともに変化します。お子様の成長、進学や就職による独立、そして将来的な介護の必要性など、さまざまな変化に対応できる柔軟性を持った間取りを計画することが重要です。
子ども部屋の可変性
小さなお子様がいる場合、当面は大きな一つの部屋として使い、成長に合わせて間仕切りで分割できるような設計にしておくと便利です。将来的に子どもが独立した後は、再び一つの部屋として使ったり、親世帯の居室として活用したりできます。
介護対応の準備
将来的に親世帯に介護が必要になった場合を想定して、寝室の近くにトイレや洗面所を配置したり、車椅子での移動を考慮した廊下幅を確保したりしておくと安心です。
5. 二世帯住宅の建築費用と資金計画
平屋と2階建ての建築費用比較
二世帯住宅の建築費用は、選択する構造や間取りパターンによって大きく変わります。
ここでは、平屋と2階建ての建築費用の違いについて詳しく解説します。
平屋の建築費用の特徴
平屋の場合、基礎工事と屋根工事の面積が2階建てより大きくなるため、坪単価は2階建てより10~15万円程度高くなるのが一般的です(※2)。例えば、50坪の二世帯住宅を建てる場合、平屋では2,500万円~3,500万円程度、2階建てでは2,200万円~3,200万円程度が目安となります。
ただし、平屋には構造的なメリットがあります。階段が不要なため、その分の費用(約30~50万円)が削減でき、構造的にもシンプルで安定しているため、工期の短縮につながる場合があります。
2階建ての建築費用の特徴
2階建ての場合、基礎面積と屋根面積を抑えられるため、坪単価は平屋より安くなります。しかし、階段の設置費用や2階部分の構造補強、上下階をつなぐ配管・配線工事などの費用が追加で必要になります。
また、2階建ての場合は外壁面積が多くなるため、外壁工事や将来的なメンテナンス費用も平屋より高くなる傾向があります。
※2 あくまで目安であり、実際は構造や設備仕様、土地条件などにより変動します
二世帯住宅で活用できる補助金制度
二世帯住宅を建てる際に活用できる補助金制度があります。これらの制度を上手に活用することで、建築費用の負担を軽減できます。
住宅ローン減税
二世帯住宅でも、一定の条件を満たせば住宅ローン減税の対象となります。完全分離型の場合、各世帯が独立して住宅ローン減税を受けられる可能性があります。
地域型住宅グリーン化事業
省エネ性能や耐久性に優れた住宅に対する補助金制度です。ZEH基準を満たす住宅や長期優良住宅の認定を受けた住宅が対象となります。
自治体の補助金制度
福岡県内の多くの市町村で、二世帯住宅や多世代住宅に対する独自の補助金制度が設けられています。例えば、福岡市では「多世代住宅取得支援補助金」として最大30万円の補助金が受けられる場合があります(※3)。
これらの補助金制度は年度によって変更される場合があるため、計画段階で最新の情報を確認することが重要です。
補助金情報については「【2025年最新】福岡で注文住宅を建てる時に使える補助金は?」の記事をご覧ください。
※3 補助金の詳細は各自治体に確認してください。申込状況により受給できない場合があります
親世帯との資金分担の考え方
二世帯住宅では、親世帯と子世帯が資金を分担して建築するケースが多くあります。
資金分担の方法や割合について、事前にしっかりと話し合っておくことが重要です。
建築費用の分担方法
一般的には、建物部分の費用を使用面積に応じて分担する方法や、親世帯が土地代を負担し、子世帯が建物費用を負担する方法などがあります。重要なのは、お互いが納得できる公平な分担方法を見つけることです。
住宅ローンの組み方
二世帯住宅の住宅ローンには、親子リレーローンや親子ペアローンなどの特別な商品があります。これらを活用することで、通常より有利な条件でローンを組める場合があります。
将来の相続対策
資金分担の方法は、将来的な相続にも影響します。税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、相続税対策も含めた資金計画を立てることをおすすめします。
6. 理想的な二世帯住宅を実現するための進め方
家族全員での要望整理の重要性
二世帯住宅の成功は、計画段階での家族間の意見調整にかかっています。
親世帯・子世帯それぞれの要望を整理し、優先順位を決めておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
生活スタイルの確認
まず、それぞれの世帯の生活リズムや生活スタイルを確認しましょう。朝型・夜型の違い、食事の時間、入浴の時間、来客の頻度など、日常生活のパターンを把握することで、間取りプランに反映できます。
将来の生活設計
10年後、20年後の家族構成や生活スタイルの変化も想定しておきましょう。子どもの成長、親の介護の可能性、退職後の生活など、長期的な視点での計画が重要です。
価値観の共有
家族の絆を重視するか、プライバシーを重視するかなど、住まいに対する価値観を共有しておくことで、間取りプランの方向性が決まります。
プラスリッコでは、ご家族全員が参加できる設計打ち合わせを重視しています。
モデルハウス「アトリエ博多」では、様々な生活スタイルに対応した空間を体感していただけるため、具体的な暮らしのイメージを共有しながら打ち合わせを進められます。
注文住宅で叶える理想の二世帯住宅
二世帯住宅は、それぞれの家族の生活スタイルや要望に合わせた細やかな配慮が必要な住宅です。そのため、注文住宅での建築が最も適していると言えるでしょう。
オーダーメイドの間取り設計
注文住宅なら、家族構成や生活スタイルに合わせた完全オーダーメイドの間取りを実現できます。例えば、親世帯が趣味の部屋を希望する場合や、子世帯が在宅ワーク用の書斎を必要とする場合など、一般的な間取りでは対応できない要望も叶えることができます。
土地に合わせた最適設計
土地の形状や方位、周辺環境に合わせて建物を設計できるのも注文住宅の大きなメリットです。変形地であっても、その特徴を活かした魅力的な住まいづくりが可能です。
プラスリッコでは、中庭を中心とした平屋の設計を得意としており、限られた敷地でも光と風を取り込む開放的な住まいを実現しています。福岡の気候風土に適した設計ノウハウと、二世帯住宅の豊富な実績を活かし、理想の住まいづくりをお手伝いします。
信頼できる住宅会社の選び方
二世帯住宅は通常の住宅よりも複雑な要素が多いため、経験豊富で信頼できる住宅会社を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考に、慎重に検討しましょう。
二世帯住宅の施工実績
二世帯住宅の設計・施工実績が豊富な会社を選びましょう。実際に建てられた住宅を見学できる機会があれば、積極的に参加することをおすすめします。
保証・アフターサービスの充実度
二世帯住宅は長期間住み続ける住宅です。建物の保証期間や住宅設備の保証内容、定期点検やメンテナンス体制など、アフターサービスの充実度も重要な判断基準です。
設計提案力と対応力
複雑な要望を整理し、最適な提案ができる設計力も重要です。また、建築中の変更要望にも柔軟に対応できる体制があるかどうかも確認しましょう。
地域密着性
地域の気候風土や建築基準、補助金制度などに精通した地域密着の住宅会社を選ぶことで、より適切な提案を受けることができます。検討している住宅会社の施工事例を見て、理想に近いものがあるか探してみるのも良いでしょう。
7. まとめ|二世帯住宅で実現する、家族それぞれの豊かな暮らし
平屋の二世帯住宅は、バリアフリー性や家族間のコミュニケーション、構造的な安定性など、多くのメリットがあります。福岡の温暖な気候を活かした中庭のある設計なら、光と風を取り込む開放的な住まいを実現でき、世代を超えた家族の豊かな暮らしをサポートします。
建築費用や補助金制度、資金計画についても、事前にしっかりと検討し、家族全員が納得できる計画を立てることが重要です。
特に親世帯と子世帯の資金分担については、将来的な相続も見据えた専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
二世帯住宅は、一般的な住宅よりも複雑な要素が多い住まいです。だからこそ、経験豊富で信頼できる住宅会社と一緒に、時間をかけて丁寧に計画を進めることが大切です。
完成した時に「建てて良かった」と心から思える住まいづくりを目指しましょう。
常設モデルハウス「アトリエ博多」では、実際の暮らし方を体感していただきながら、具体的な住まいづくりの相談ができます。二世帯住宅をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。家族みんなが笑顔で暮らせる、理想の住まいづくりを一緒に進めていきましょう。
アトリエ博多の詳細はこちら







